「あの人、なんであんなに仕事が早くて、信頼されてるんだろう…?」
そう感じたことはありませんか?
私はとある単純作業をしていたときに、そんな“できる人の特徴”のヒントを見つけました。
ポイントは「全体を意識しているかどうか」。
一見地味で退屈な作業でも、全体の流れを考えるだけで判断力が上がり、仕事の効率も信頼度も大きく変わってくるんです。
今回は、そんな私の体験から見えた「できる人に近づくための視点」についてご紹介します。
単純作業の中で“できる人の思考“に気付いた体験談
「請求書や領収書のPDFを見て、記載されている日付や金額などを入力する」という作業を手伝っていた時のこと。
基本的にはマニュアルに沿って、データを入力していくだけの簡単な仕事ですが、たまにイレギュラーでそれ以外の書類が混ざっていることがあります。
私の場合は稟議書が混ざっていました。(稟議書とは社内で決裁を取るための文書で、経理処理には関係ないもの)
最初見たときは「稟議書の入力なんか知らないぞ」と、マニュアルに確認漏れがないか読み返してみましたが見つからず、混乱しました。
そこで一度、落ち着いて考えてみました。
「なぜこの仕事をしているのか」を理解すると、全体像が見えてきて、自分に求められている仕事内容も明確になります。
そうすると、マニュアルに記載がない「稟議書」というイレギュラーが発生しても、おそらく関係ない書類だと判断することができ、無駄に迷うことなく「入力不可」としてすぐに次に進むことができます。
また、そうして自分の仕事に意味を見出せると、同じ仕事をしていても、やる気が出てくるから人間は不思議です。
勉強でも通じる!全体像を意識することの強み
仕事のみならず、受験勉強などにも「全体像を把握すること」は大事です。
例えば日本史で、天保の改革(1841年/水野忠邦)を覚えるとします。
ただ「いやしい(1841)水野の天保の改革」と暗記するだけでは、すぐ忘れますし、応用が効きません。
「天保の改革」の背景には、天保の大飢饉(1833〜1837)があって庶民の生活が崩壊していたことがあり、幕府はこれを立て直すために倹約令を出したり、株仲間による価格操作を取り締まったりしました。
このように全体像を理解していれば、知識も定着しやすいですし、多少ひねった問題を出されても対応することができます。
「何も考えずにただ数字と文字を暗記する人」と「全体像を把握して繋がりで覚える人」、どちらが有利かは言うまでもありません。
”全体を考える人“は成長も信頼も得やすい理由
実際に私の本業での同僚や後輩を見ていても、「全体を意識して仕事をしている人」と「何も考えずに仕事をしている人」は見ていればわかりますし、成長速度にも明らかに差があります。
「全体を意識して仕事をしている人」は、次の人がやりやすい形に整えて仕事を渡しますし、イレギュラーがあった場合も自分の頭で判断して対処できます。
そういう人はやはり周囲の信頼も得やすいですし、人が集まります。
一方「何も考えずに仕事をしている人」は、周囲にもバレていますし、重要な仕事を任せてもらえないケースも多いです。
このあたりの感覚は、おそらく皆さんもなんとなく分かるのではないでしょうか。
まとめ
勉強でも、仕事でも、人生のあらゆる場面で「全体像を把握すること」は必ず役に立ちます。
新社会人など、本当に最初の最初は、指示されたことしかできないのは仕方ないですが、「なぜこの作業をするのか?」を考えるだけでも何も考えない人とは差が付きます。
若いうちからの「少しの意識の違い」が、長い社会人生活を経ていくうちに大きな差となり、数十年後には「できる人」か「窓際社員」かという他者の目にも明らかな形で表れます。
わからないなりに、作業の先にある「目的」を意識し、全体を把握する努力をしていきましょう。
そうすれば、数十年後にはきっと「できる人」として周囲から信頼される人材となっています。
全体を把握して、自分に求められている仕事を理解して、一つ一つこなして、成長していきましょう。
それでは。
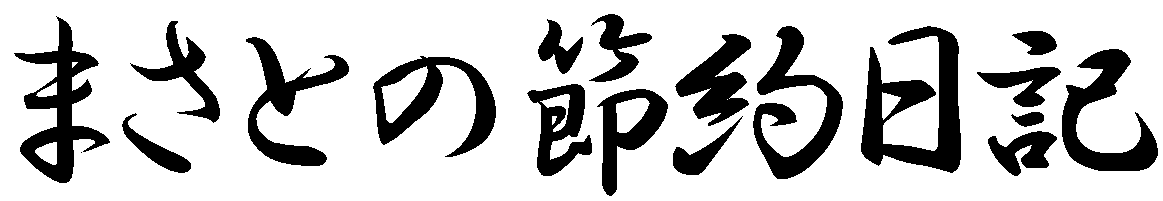
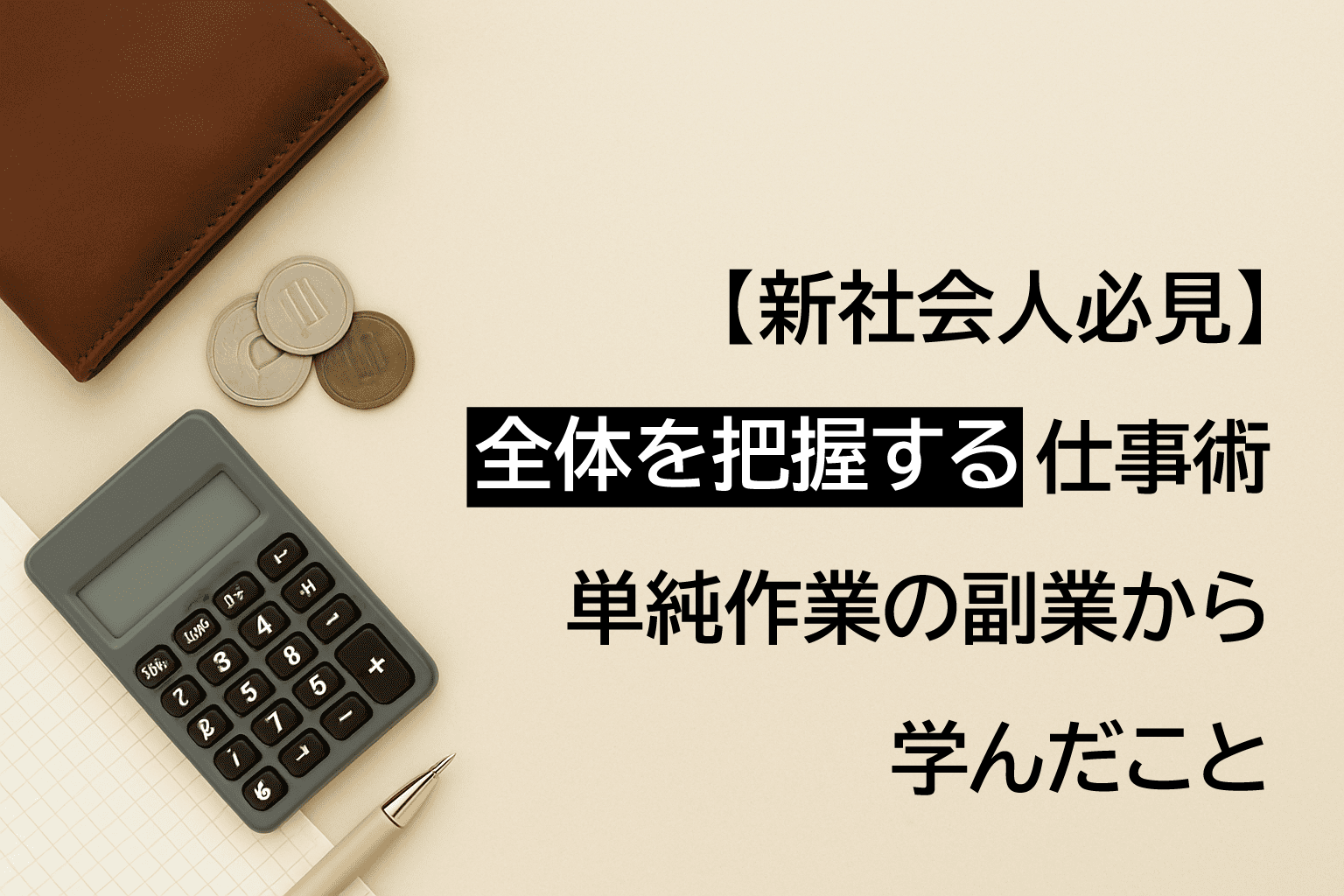
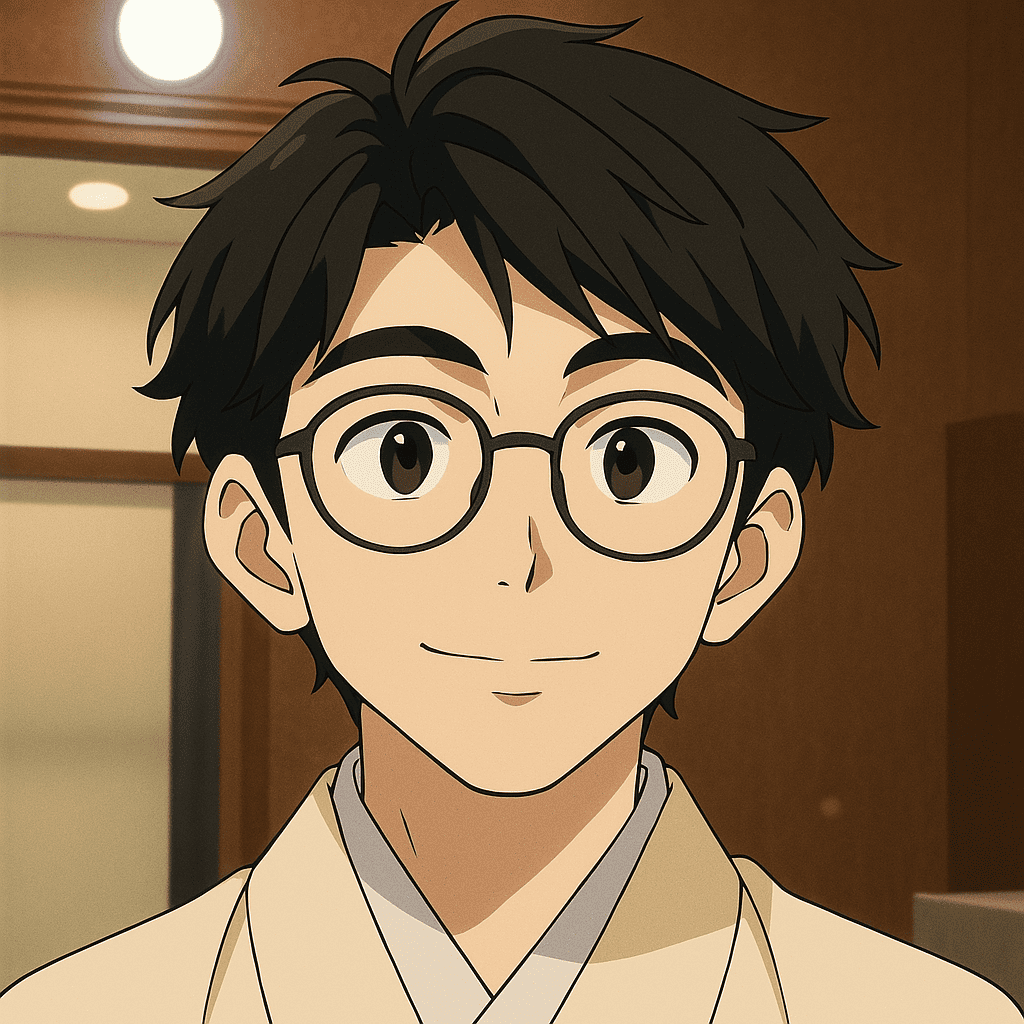
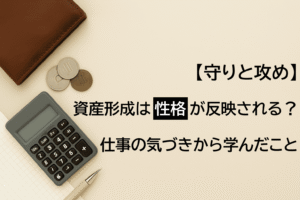
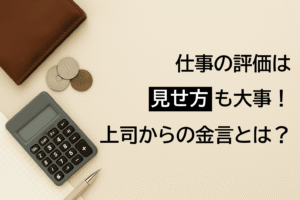
コメント